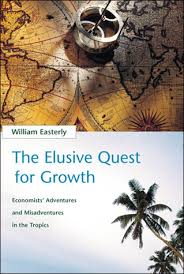一冊
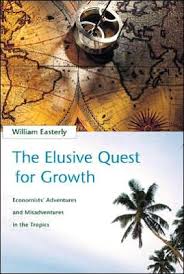 は、William Easterlyという世銀エコノミストの書いた“The Elusive Quest for Growth”。6月7日のエントリーでも触れたとおり、なぜ多くの途上国で経済成長の模索が失敗に終わったのかが書かれている(『エコノミスト 南の貧困と闘う』という邦題で訳本も出ているみたい)。全編を通してのキーワードは“incentive”。政府も含め、あらゆる主体は“incentive”に導かれて行動する。先進国ドナーによる多くの援助は、その事実を無視(或いは軽視)して行われてきたため、大した成果をあげることができず、それどころかマイナスの影響を与えることも多かった――というのが著者の主張。
は、William Easterlyという世銀エコノミストの書いた“The Elusive Quest for Growth”。6月7日のエントリーでも触れたとおり、なぜ多くの途上国で経済成長の模索が失敗に終わったのかが書かれている(『エコノミスト 南の貧困と闘う』という邦題で訳本も出ているみたい)。全編を通してのキーワードは“incentive”。政府も含め、あらゆる主体は“incentive”に導かれて行動する。先進国ドナーによる多くの援助は、その事実を無視(或いは軽視)して行われてきたため、大した成果をあげることができず、それどころかマイナスの影響を与えることも多かった――というのが著者の主張。その前に読んだ『クラウド化する世界』(後述)があまりに素晴らしかったので余計にそう思ったのかもしれないが、経済学を一通り学んできた人間にとっては、ある程度当たり前に思える主張が多く、「目からウロコ」な記述には残念ながら出会うことができなかった。ただ、具体例の提示が多いので、ものを考えるきっかけを得るには悪くない本。「前時代の遺物を抱えていない途上国は、先進国よりむしろスムーズに新技術に適応できる可能性がある」と述べられたChapter 9は、裏から読めば、如何に先進国でinnovationを起こすのが大変かというようにも読め、日本の現状を思うと非常に耳の痛い話。
もう一冊
 は、Nicholas Carrの『クラウド化する世界』邦訳版(原題“THE BIG SWITCH”)。この二年くらいの間に僕が読んだ本の中で、一番と言っていいくらいにおもしろい一冊だった。
は、Nicholas Carrの『クラウド化する世界』邦訳版(原題“THE BIG SWITCH”)。この二年くらいの間に僕が読んだ本の中で、一番と言っていいくらいにおもしろい一冊だった。「クラウド(=雲)コンピューティング」と呼ばれる現代のコンピュータ社会を、いろんな側面から解き明かした一冊で、無理やり分類すれば、数年前に大ヒットした梅田望夫氏の『ウェブ2.0』と同じジャンルに位置づけられるのかも知れない。ただ、あの本より数倍深い(←正直に言うと僕も、当時は、『ウェブ2.0』に熱狂した)。
前半では、いま、webやコンピュータをとりまく世界で何が起こっているのか、またそれは何を意味し、その結果としてどんなことが可能になるのかが、総じて肯定的なトーンで描かれている。反面、後半では、コンピュータのクラウド化によって、現代人や現代社会(←「ネット社会」ではなく、社会そのもの・社会全体)がどのように変化していくのかが予測的に描かれており、底流に流れるトーンはどちらかというとネガティブ。クラウド化が人間社会にもたらすものは、決してプラスの要素だけではなく、マイナスの要素もあり、それらの一部は、人間や人間社会の本質的な部分にも関わるものだということが率直に述べられている。(だからといって、「クラウド化を止めるべき」なんていうナイーブかつ無意味な主張はもちろんなされていない。)
前半部分では、コンピューティングのクラウド化のアナロジーとして、発電システムが分散型から集中型へと推移していった歴史的経緯がかなり詳しく紹介されている。この箇所(特に、中央発電システムに先鞭をつけたインサルの事例)は、「要するにイノベーションってどういうこと?」かを極めて具体的に現している。どんな分野においてであれ、「イノベーション」というものを考えるときに、大いに参考になる著述だと思う。
斯く具合に、前半は前半で、示唆に富んでいて非常に面白いのだが、本著の心髄はむしろ後半部分にある。後半は、「ネット論」「コンピュータ論」の範疇を超え、「社会論」或いは半ば哲学の域に達しているとさえ思える。そのくらいに深い。こんな文章は、ただ一つの分野に精通しているだけの人にはまず書けないだろう。分野を超えた膨大な知識を一個の脳ミソの中に貯め込み、咀嚼して初めて紡ぎだされる文章ではないかと思う。
僕には、これ以上、この本を解釈したり要約したりする力量はないので、代わりに、本著からの引用を一節。
インターネットの能力、範囲および有用性の拡大がもたらしたもっとも革命的な結果は、コンピュータが人間のように考え始めることではなく、我々がコンピュータのように考えることなのだ。リンクを重ねるたびに、我々の頭脳は「“ここ(HERE)”で見つけたもので、“これを行え(DO THIS)”、その結果を受けて、“あちら(THERE)”に行く」ように訓練される。その結果、我々の意識は希薄になり、鈍化していくだろう。我々が作っている人工知能が、我々自身の知能になるかもしれないのだ。


 三木氏によると、こういった市場価格の下落に加え、以前はプライマリーCER(CDMプロジェクトの実施に伴って発行されるCER)よりも割高だったセカンダリーCER(既に発行済みのCERの転売商品)の価格が、ここにきて、プライマリーと同水準まで下がってきたため、リスクの伴うプライマリーCERの購入を見送るバイヤーが増加しているとのこと。「この状態が長く続けば、CDMプロジェクトへの資金の出し手がいなくなり、CDMプロジェクトの開発が停滞することが懸念される。」 (by 三木氏)
三木氏によると、こういった市場価格の下落に加え、以前はプライマリーCER(CDMプロジェクトの実施に伴って発行されるCER)よりも割高だったセカンダリーCER(既に発行済みのCERの転売商品)の価格が、ここにきて、プライマリーと同水準まで下がってきたため、リスクの伴うプライマリーCERの購入を見送るバイヤーが増加しているとのこと。「この状態が長く続けば、CDMプロジェクトへの資金の出し手がいなくなり、CDMプロジェクトの開発が停滞することが懸念される。」 (by 三木氏)


 その中でもアフリカのシェアは非常に小さい。マーケット全体のわずか1%。アフリカのシェアが少ないのは、CDMも同じなのだが、VCMがCDM市場と違うところは、30%弱をUSA産のクレジットで占められているということ。CDMのような、京都議定書に基づく制度ではないので、アメリカ国内での削減からだって、クレジットをつくることができるわけだ。また、VCMクレジットの買い手は、基本、排出削減義務を負っていない者(アメリカの企業がその典型)で、文字通り“voluntary”に買うわけだから、買い手が1 t-CO2あたりのクレジットに払ってもいいと考える額は、CDMよりも小さいだろう。そう考えると、VCMにおけるアフリカ産クレジットの割合は、単にいま小さいというだけでなく、今後も、小さいままで推移する可能性が高い。そんな気がする。
その中でもアフリカのシェアは非常に小さい。マーケット全体のわずか1%。アフリカのシェアが少ないのは、CDMも同じなのだが、VCMがCDM市場と違うところは、30%弱をUSA産のクレジットで占められているということ。CDMのような、京都議定書に基づく制度ではないので、アメリカ国内での削減からだって、クレジットをつくることができるわけだ。また、VCMクレジットの買い手は、基本、排出削減義務を負っていない者(アメリカの企業がその典型)で、文字通り“voluntary”に買うわけだから、買い手が1 t-CO2あたりのクレジットに払ってもいいと考える額は、CDMよりも小さいだろう。そう考えると、VCMにおけるアフリカ産クレジットの割合は、単にいま小さいというだけでなく、今後も、小さいままで推移する可能性が高い。そんな気がする。